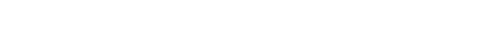C.S.ルイス「悲しみをみつめて」を読む
【英知の言葉】古くから、人は愛する人との別れを嘆き、悲しんで来ました。古今東西のグリーフの表現は、豊かで、幅広く、先人の英知に満ちています。この英知のセクションには、先人の考えた、死とは何か、生とは何か、悲しみと向き合うとはどういう事か、といった見識が含まれています。言葉にならない悲しみに、言葉を与える作業に貢献できればと考えています。
まだまだ小さなコレクションですが、グリーフに関連する英知の言葉を集めています。数が増え次第、カテゴリーも増やしていく予定です。
C.S.ルイスについて

C.S.ルイス
C.S.ルイスは英国の神学者、英文学者で、近年映画化された「ナルニア国物語」の原作者として知られています。
一度も結婚をしたことのなかったルイスは、55歳の時、以前から文通をしていたアメリカ人の詩人で作家である、ジョイ・デイビッドマンと彼女が旅行で英国を訪れた際に出会い、その知性とユーモアに魅かれ、深い友情に結ばれます。
しかし、デイビッドマンに不治の骨のがんが見つかると共に二人の関係は深まり、ルイスとデイビットマンは病院のベッドで友人の牧師の立会いの下結婚します。ルイス60歳の時の事でです。その後、デイビッドマンの病状は少し良くなり、何年かは夫婦として過ごすことになりますが、デイビッドマンは1960年、ルイス63歳の時に45歳で亡くなります。
彼女の死後、ルイスは4冊のノートに自分の死別の経験についてメモを書きとめます。非常に個人的で「生」なメモであり、当初出版の予定は全くなかったと思われますが、最終的にこの文章はルイスの在命中に、匿名で「悲しみをみつめて」として出版されます。
これほどの文学的、哲学的才能を持った人が、喪失体験、グリーフを真正面から描く事は稀で、その文章は、表現豊かで、的確、しかも英国人特有のニヒリズムにあふれ、内省的な素晴らしい内容です。例えば、大切な人を失った人がしばしば戸惑う出来事、「なぜあれほど愛した人の顔を思い出すのがこれほど難しいのか」といったことにもルイスなりの解釈があり、なるほど、と思わずにいられません。
また、読み進めるうちに、ルイスの心持が、徐々に喪失との和解、死者との対話に向かう様子がうかがい知れ、思いを記す事でのグリーフ作業を垣間見ることが出来ます。ここでは、その中から選んだメモを紹介します。(引用は全文ではないこともあります。)
全て出典は、「悲しみをみつめて」:新教出版社:西村徹 訳:1976、より。文中の「H」がデイビッドマンの事。
大丈夫だと思ったとたんに
まったく思いがけなくときにわたしの内なるなにものかが、けっきょくわたしは、たいして、それほどたいして、気にかけてはいないのだと、わたしに納得させようとすることがある。愛が人生のすべてではないのだと。わたしはHに逢う前から幸福であった。わたしはいわゆる「生きる娯しみ」にはめぐまれている。人はこのようなことも乗り切るものだ。わたしだってそんなにへまはやるまい。人はこの声に耳を貸すことを恥じるけれど、ちょっとの間ならその声にも、もっともな言い分がありそうにきこえる。かと思うと、灼熱した記憶の刺突の不意打ちに見舞われて、この「常識」はすっかり炉のロの蟻のように消えてしまうのだ。
困惑の種
それは子供たちだけとはかぎらない。わたしが妻を失った、その奇妙な副産物は、わたしが出あうだれかれにとっても、わたしが困惑の種になっているとわかることだ。仕事をしても、グラブでも、通りでも、ひとびとが、わたしに近寄りながら、「あのことについてなにか言おう」か言うまいか、なんとか覚悟をきめようとしているのがわかる。もし彼らが言えば言ったで、言わねば言わないで、わたしはそれがいやだ。ある人はまるっきり逃げ出してしまう。Rは一週間わたしにあわないようにしていた。まるでわたしが歯医者ででもあるかのように、近づいてきて、真赤になって、お悔みを言い、それから非礼にならぬ程度に、できるだけ速くバーへ逃げこんでしまうような、育ちの良い、まだ少年ぐらいの青年が一番好ましい。多分、遺族というものは、伝染病患者のように特別な収容所に隔離されねばなるまい。
(不適当な表現を変更しています)
不吉な者
ある人々にとっては、わたしは困惑の種どころではすまないのだ。わたしはしゃれこうべだ。わたしは、幸福な夫婦づれにあうと、二人の考えていることが分かるのだ。「わたしたちのどっちかが、いつかは今のあの人のようにならなきゃならないんだ」と。
思い出せない理由
わたしは、彼女の、ろくな写真を持ってはいない。わたしは心の中に彼女の顔をはっきり見ることさえできない。(中略)なるほど、説明はごく単純だろう。わたしたちは、いちばんよく知っている人々の顔を、あまりにさまざまに、あまりに多くの角度から、あまりに多くの見方で、あまりに多くの表情を ― 覚めて、眠って、笑って、泣いて、食べて、話して、考えている所を ― 見てきたものだから、すべて、その印象が記憶の中にいちどきになだれこんで、おたがいを消し合ってすっかりぼやけてしまうのだと。それでも彼女の声は、いまもってまざまざと残っている。その声を思い出すと ― するとわたしは今にも、すすり泣く子どもにかわってしまいそうだ。
自分の苦しみばかり
はじめてわたしはふり返り、この覚え書を読み返した。何たることか、わたしの語り口をきけば、Hの死の、わたしにおよぼす影響がいちばん問題であったようにだれしもが思うだろう。彼女の立場はかき消えてしまったかのようだ。「まだまだ生き足りなかったわ」と、彼女が声高く叫んだ、あの苦渋の時をわたしは忘れたのか。
彼女の記憶
(十年合わなかった人に会った時)想像でない実物の彼が全貌を現わしたときの印象全体は、ここ十年わたしの抱きつづけてきた心象とは、まるでびっくりするほどちがっていたのだ。わたしの思い出の中のHにも、このことが起こらぬとどうして望めよう。いちはやくそれは起こっているのではないとどうして思えよう。ゆっくりと、静かに、雪のひとひらのように ― 夜もすがら降りしきる雪の、小さなひとひらひとひらのように ― わたしという、わたしの印象、わたしの選択という、ちっぽけなひとひらひとひらが、彼女の心象の上に降り積ってゆくのだ。真の姿は、ついにはすっかり隠されるだろう。実のHに十分、いや十秒でも会えば、すべて正しい姿に戻りはするだろう。またしかし、たとえその十秒がわたしにゆるされたとしても、一秒の後にはまた、そのちっぽけなひとひらが降りはじめることだろう。
考えずに済むと思えば
いつもHのことを考えているといえばうそになる。仕事や人と会って話すので、それはできない。しかし考えていないときが、たぶん、わたしにはいちばんつらいときだ。なぜならそのとき、理由は忘れてしまっているが、漠然とした、変調があるという、なにかしら狂いがあるという感じが、すみずみまでひろがっているからだ。怖しいことはなにひとつ起こらず、朝食のとき話してみても、なにひとつ格別のこととは、きこえそうなこともなくて、ただ全体の、気分、肌ざわりがやりきれない夢のようだ。これがちょうどそれだ。ななかまどの実が赤らむのを見ると、ふとなぜかしら、ほかでもない、その赤い実が気をめいらせるのだ。時計が時を告げる音をきいても、前にはいつもきこえてきた、その音の持つなにかが、いまはきこえてこないのだ。この世の中がこんなにもそっけなく、みすぼらしく、しおたれてみえるのは、いったい、その、どこが狂っているのだろうか。するとわたしは思い出すのだ。
私のための復活
自分の悩みのことを多く考えて彼女の悩みを考えること、はるかに少ないとは、いったいわたしは愛する者のどういう類なのだろう。「戻ってきておくれ」と呼ぶ、正気の沙汰ならぬ声さえすべてわがためなのだ。よしんば帰ってきたとして、それが彼女にとって良いことかどうか、わたしは一度も尋ねてみたことさえない。わたしが彼女に戻ってきて欲しいのは、わたしの過去の復活の一要素としてなのだ。およそそれより悪いことを彼女に望みえたろうか。
初めての交流
まったく思いもよらぬことが起こった。今日、朝まだきのことであった。それ自体は何の不思議もない種々の理由から、それまでの幾週間ものあいだよりも、わたしの心は軽かった。ひとつには、おびただしい、ただ肉体的な疲労から恢復しつつあるからだろう。またわたしは昨日、非常にくたびれはするが非常に健康な十二時間をすごし、そして夜はひときわぐっすり眠った。それに、低くたれこめた灰色の空と、しめっぽくなまあったかい日が、ぐずぐずと十日もつづいたあとで、日は輝き、そよ風のわたる日であった。そして突如、それまでの、Hを悼む心のもっとも少ないそのときに、わたしは彼女をもっともよく思い出したのだ。まったく、それはなにか(ほとんど)記憶以上のもの、即座の、有無を言わせぬ印象であった。一つの出あいのようだと言えば言いすぎにはなろう。しかしそういう言葉を使いたくなるようなところがあった。あたかも悲しみが晴れあがって障壁をとりのぞくかのようであった。
しがみつくから溺れる
たすけを求める叫び声のほかには、人の魂のうちに何もないときが、ほかならぬ、神がそれを与えることのできぬ時かもしれない。しがみつき、すがりつくから、かえって、溺れる人がたすけてもらえないようなものだ。たぶんそれは自分自身がくり返す叫びにかき消されて、聴きたいものの声が聞こえないのだろう。
中断されたダンス
そしてその上でどちらかが死ぬ。そしてわたしたちはこのことを、愛が断たれたもののように、踊りが途中で止められるように、花が運悪くそのくびを折られるように、何か先を切られてそのために本来の形を失ったもののように思うのだ。そうだろうか。(中略)中途の切断でなくて一つの段階、舞踊の中断ではなくて次の舞いの型なのだ。わたしたちは、愛する者の生きているあいだは、その者によって「自己の外につれ出され」る。それからその舞いは悲劇的な型にかわって、相手の肉体は姿を消しても、あいかわらず自己の外につれ出されるようにならねばならず、ふたりの過去を、ふたりの追憶を、ふたりの悲しみを、悲しみからの救いを、ふたりだけの愛を、愛することに舞い戻るのでなくて、彼女その人を愛するようにならねばならない。
切断された肢
立直りはそんなに早いだろうか。しかしその言葉の意味は二重だ。患者が虫垂炎の手術の後で恢復に向かうというと、片脚切断の後とではまるでちがう。その手術の後では、傷になった切り口が癒えるか、その人が死ぬか、どちらかだ。もし癒えれば、すさまじい不断の痛みはとまるだろう。まもなく力をとり戻して、義足でごつごつ動きまわれるだろう。彼は「立ち直った」のだ。しかしおそらく生涯にわたって切口の痛みはくり返すだろうし、あるいはかなりひどく痛むこともあろう。そして、いつだって一本足かわりはあるまい。それを忘れることはまずあるまい。湯にはいっても、着物を着ても、すわっても、また立っても、寝床にはいってさえ、まるきり様子がちがうだろう。生活様式全体が変わるだろう。かつて不思議とも思わなかったあらゆる種類の悦楽と活動は、文字通り奪いとられずにはおかないだろう。義務またしかり。たった今わたしは松葉杖にすがって動きまわることを学んでいる。あるいはやがて義足が貰えるだろう。しかし二度と二本足にはならないのだ。
死せるものとの結婚
わたしたちは一体であった。今二つに裂かれた以上、完全無欠な一体だなどとは言いたくない。しかもなお結婚は、そして愛は、つづいてゆくのだ。だからなお痛みはつづくだろう。しかしわたしたちは、自分を知るならば、少しも痛みゆえの痛みを求めはすまい。結婚のつづくかぎり痛みは少ないに越したことはない。そして死せる者と生ける者との結婚にも、よろこびは多いに越したことはない。
悲しみは死者とのつながりを断ち切る
あらゆる点でそれに越したことはない。すでにわかったように、熱っぽい悲しみというものは、わたしたちを死者と結びあわせないで断ちきるからだ。これはますますはっきりしてくる。悲しみを覚えることのもっとも少ないときにこそ ― 朝の入浴のときなどたいていそうだが ― Hはまったく生き生きと、すなわち、われならぬ他者として、わたしの心におしよせる。いっとう参っているときのように、わたしのみじめたらしさによって先細りになった遠景の中に、哀傷にみち、粛然たる面持があらわれるのでなくて、まぎれもない彼女自身の姿がある。これはじつに心を鼓舞するものだ。
螺旋を描く痛み
すばらしいもくろみだ。しかし、やれないのが残念だ。今夜はまた、新しい悲しみの百鬼夜行の跳梁が始まった。狂気の言葉、沈痛無念、肺腑のおののき、仇しき悪夢、溺るる涙。悲しみの中では何物も「釘づけ」にはならぬからだ。たえず、一つの局面を脱しても、きっと元に戻るのだ。転々と。すべてが繰り返す。わたしは輪を描いているだけなのか、それとも螺旋上を進んでいると考えていいのだろうか。
失い続ける
いったい、いくたび、このひどいむなしさは、まるで新しいことのように、わたしをおどろかせ、「今の今まで自分の失ったもののことに気づかなかった」と言わせるのだろうか、そしてそれは、いつまでもこうなのだろうか。同じ一つの脚が何度でも切られるのだ。くり返し、くり返し、肉に突き立てられるメスの感じは初めてのときと同じだ。
悲しみはいつまでも続く歴史
わたしは一つの心的状態を描きうると、悲しみの地図を作りうると、思ったのだった。悲しみは、しかしけっきょく、状態でなくて過程なのだ。地図ではなくても歴史でなければならぬし、歴史なら、どこかまったく任意の点で書くのをやめないと、やめる理由がなくなってしまう。毎日なにか新しいことを書かねばなるまい。悲しみはながい谷、どこを曲がってもまるで新しい風景のひらける、まがりくねった谷に似ている。すでに記したように、あらゆる曲りめがそうだとはかぎらない。ときには、だしぬけに、それと反対になることもあって、何マイルも後にしてきたと思っている、それとまったく同じような場所が目の前に現われることもある。そんなとき谷は堂々めぐりの掘割ではあるまいかと思ってしまう。ところがちがうのだ。ところにより堂々めぐりもあるが、道筋はくり返しはしない。
死者には私たちが見える
死者にはわたしたちが見えると、しばしば考えられる。そしてわたしたちは、それが道理か否かは別として、かりにも死者にわたしたちが見えるのなら、前よりはっきり見えるのだと思う。今Hには、わたしの愛と彼女がかつて呼び、わたしが今も呼ぶもののうちに、どれほど、うたかたに似た、まがいものがまじっていたか、はっきりと見えるのだろうか。それならばそれでよい。ねえおまえ、うんとしっかり見ておくれ、たとえできても、かくれたりはしたくない。わたしたちはおたがいを理想化など、しはしなかった。秘密など、持つまいと努めた。もう前から、わたしのいけないところは、たいていおまえにはわかっていた。さらに悪いところが、今おまえに見えるなら、わたしはそれをいさぎよく-認めていい。おまえにもそれはできよう。なじり、説き明かし、まゆをひそめ、ゆるすことも。なぜなら、これは愛の奇蹟の1つであり、それは両方に、しかしあるいは、とりわけ女の方に、愛に心は奪われながら、それを透して真実を見る目は曇りもせず、さりとて愛の冷えることもない力を与えるものだから。