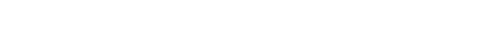グリーフワークを考察する
グリーフワークを深く掘り下げるセクションです。管理人が最も共鳴しているトーマス・アティッグの考え方を紹介したいと思います。
トーマス・アティッグによる考え方
トーマスアティッグは元ボウリング・グリーン州立大学教授。ここではその著書「死別の悲しみに向きあう」で紹介されている考え方を紹介したいとおもいます。アティッグはこのグリーフの研究家としては少数派の哲学のフィールドから、死別、グリーフについての研究をしています。
(特に断らない限り、引用はすべて「死別の悲しみに向きあう」大月書店、1998より)
謎に立ち向かう
トーマスアティッグは死別とそれを取り巻くグリーフは「謎」に似ており、その謎に立ち向かうのに必要なのは「世界を学びなおす営みである」という。
アティッグは「私たちが悲しむとき、たんなる問題ではなく、謎が人生の中心的位置を占める。問題とは、解決し、決定的な形で答え、制御し、管理し、征服することができる試練だ。私たちは、満足できる解決法を見つけ、先に進む。これに 対して、謎は、それほど断固として対処することができない試練を突きつける」という。謎は単純な問題でなく、しつこく、姿を変えながら私たちの前に現れる、私たちの理解を超えた謎であり、解いたり、制御したりすることは出来ないのだという事を知る必要がある、と言う。
現実 ― 死 ― は考え方によっては変えられない事は明白だが、その謎に繰り返し立ち向かう事は可能だ、とアティッグは考えている。その過程で人は一時、役立つ生き方を学びぶことが出来た、と感じるが、再びコースを変えなければならないことに気づく、という事を人生を通じて繰り返しながら、グリーフワークを通して世界を学びなおすのだと。「私たちの思考で現実を変えることはできなくても、人は適切な対応を打ち出すことはできる。私たちの考えに根本的な 限界があるにもかかわらず、最善を尽くして、どんな困難な経験にも耐え抜き、学びなおす努力をすることにはつねに意味がある。」
グリーフワークは能動的な営み
アティッグは、段階論的、フェーズ的な考え方に批判的だが、彼の一番のポイントは、こういった考え方はグリーフを受け身な事だととらえすぎるのだという。確かに、喪失とその後の衝撃を人は、外部の力によって加えられたものとしで経験するという点はアティッグも同意している。この経験には選択の余地がなく、自分にはどうにもならない出来事、私たちがいくら切実に願っても、元には戻せない事がたくさん起こり、だから人は喪失に対して無力に感じ、恐れるのだ、と。そして、喪失によって一変した現実のなかで、今まで持っていた願望や習慣を保ちつづけることは何の意味もなさないが、それでも、元の世界に戻れるのではないかと、今までのやり方にしがみつき、裏切られてはグリーフを感じるのだ、という。
アティッグは、死んだ人なしでやっていくには、「いつまでもこの受身な状況に浸っていたい」という願望に抵抗し、対処することを選ばなければいけない、という。そして対処する営みとしてのグリーフワークを行うには、私たちが積極的に反応し、精力を注ぎ込み、課題に取り組むことが必要で、日々の生活のパターン、遺された家族との関係、友人との関係、故人との関係、仕事、趣味、根本的な信念を見直し、何らかの位置づけを行って、世界を学びなおすのである、という。
そして、段階論、フェーズ論に対して、課題と言う考え方は、「~~をする」という積極的な姿勢を持つという意味で、ウォーデンの4つのタスクを評価している。
グリーフワークは選択ができる
そして、死が、自分の「選択の余地がない」状態で起こってしまったのとは逆に、グリーフワークは「選択の連続である」、とアティッグは言う。その選択は非常に瞬間的に、本能的にしていることも、熟慮の末に行われることも、一度した選択が失敗である事を知り、修正して選択することもある。
葬儀の最中に頑張って立派な喪主のスピーチをするのかしないのか、形見は大切にするのか捨ててしまうのかとりあえず保留にするのか、辛い気持ちを吐露することも胸の内にしまっていることもできる。ほかの人からの支援を受け入れる事も断る事もできる、亡くなった子供の部屋を片付けるのかそのままにするのか、今までの生活のパターンをすっかり変えてしまうのか一部だけ続けるのかそのまま続けるのか、生と死の意味について深く考えるのかそうでないのか。そして、人知を超えた何か、大きなものの存在を信じるのか、そうでないのか。グリーフワークは数限りない、そして難しい選択を人に突きつける。グリーフワークは能動的な営みであることをまた一つ裏付ける。
世界を学びなおす
トーマスアティッグは、世界を新たに学びなおすことは、大切な人がいない世界で、どのように存在し、振る舞うかを学ぶ作業だとした上で、いくつかの学びなおすエリアを上げているが、特に「自己を学びなおす」と「故人との関係を学びなおす」ことを重要だと考えている。
自己を学びなおす
アティッグは、喪失の体験と適応の作業を、大きなウェブ ― クモの巣のようなもの ― が大きく傷ついてしまった状態、そしてそれを修復していく作業に例えています。トーマス・アティッグは「死別の悲しみに向き合う」第5章”自己を学びなおす”の中で、非常に素晴らしいアナロジーを使ってこれを説明してるのですが、非常に文学的で、箇条書きにまとめるわけにはいきません。かなり恣意的ではありますが、ここに一つのお話としてまとめてみました。個々の糸の処理の仕方を能動的な営み、選択の積み重なりと考えると解りやすいかもしれません。
人はウェブの真ん中で、いろいろな人と経糸でつながりを持っています。つながりの強い人には、強く丈夫な糸が何本もつながっているかもしれません。その糸を通して、人は配慮の気持ち、援助、知識、励まし、激励、理想像、信頼、共感、肉体的なふれあい、そして時にはネガティブなもの、そういった様々なものを交換し、交流していきます。そして、それら経糸同志は横糸によって結びついており、人との関係はほかの物と無関係ではありえません。このウェブは今まで何年もかけて、新しい糸をかけ、ほつれた糸を繕いつつ編み上げてきた、自分と他者のつながりであり、自分の姿そのものです。このウェブの大きな一本が切れ、ウェブは大きな衝撃を受けました。ウェブはもう、半分宙ぶらりんになってしまいました。受けた一撃の大きさは、ウェブ全体を揺れ動かし、ほかの経糸も大きく揺れ動き、細い糸は切れてしまいました。
ウェブに与えられた打撃の衝撃が納まると、人はすっかり痛んでしまったウェブの修理を始めます。最初はあまりに痛んでしまったウェブに、それを繕っていこうという意欲もわかないかもしれません。それでも人はウェブの修理を始めます。以前かかっていた糸でまだ使えそうなものはそのままに、大きな裂け目にはできるだけ周りと調和するように新しい糸を、そして全体として「意味のある形になるように」、ゆっくりと糸をかけていきます。今まであった糸が緩んでいる部分は引っ張り上げる必要があるかもしれません。修復不能な糸は切ってしまう必要があるかもしれません。時間が経つにつれ、今まで細かったほかの人とのつながりが太くなったり、違った方向に糸を掛けたり、ウェブは、前とは違う形ですが、安定してきます。初めて訪れた人はそこに以前は全く違った形のウェブがあったことなど気が付かないかもしれません。それでもそのウェブは以前合った場所に存在し、人はその中心に居続けています。初めての人は言うかもしれません。「なんて素敵なウェブでしょう」。そして人は「ありがとう、いいウェブでしょう?」とほほ笑むようになるのです。
(トーマス・アティッグによる「自己を学びなおす」アイディアを【グリーフ・サバイバー】運営者が再構成したもの)
故人との関係を学び直す
人の死は、物質的な人物をこの世から奪ってしまいます。「相手がいなくなってしまったことを日々の暮らしの中で切実に感じ」、「続いていく人生の物語の中心的な登場人物を失い」、「いまは亡き人との今までの結びつき方を失う」とアティッグは言います。しかし、すべての故人との絆を断ち切る必要はないと主張します。「一方、故人が死ぬ前にその人と生きた時間失わない。その人との関係のなかで与えられたものは、何も失わない。いまや終わってしまった人生の意味は無に帰しはしない。残された私たちは、なお、いまは亡き人のインスビレーションと影響を自分の人生に取り込むことができる」。死で人生が帳消しになるのではないのです。
そして、アティッグは死者との関係をダンスに例えています。
私たちが、 他の人を気づかい、愛するとき、私たちの愛着は、いっしょに自由に動いていく踊り手がやさしく抱き合っているのに似ている。ダンスの相手の展開していく内面に対する感受性・敏感な反応に似たものが、互いを気づかい、 愛する営みに内在している。死は、気づかい愛する営みの終わりではない。死は、気づかい愛する営みをつづけながら、その形を変えていくことと両立する。私たちは、 悲しむなかで、ダンスの次のフィギュアを学ぼう、相手を失ったことで私たちの人生が一変しても、意味のある形で、いまは亡き人を気づかい、愛しつづけるやり方を見つけようともがく。悲しむなかで、離れ離れになった相手を愛するすべを覚える。
アティッグはさらに、遺された者が、故人と過ごした時間や、故人との関係のなかで与えられたものを物語に例え、「終わってしまった人生の物語を愛し、大切にする」ことが出来るという。素晴らしい物語は何度も読み返したくなるものだし、読み返すたびに新しい意味がある、という。
そして最後に、アティッグはこういう。他者を愛するとき、私たちは相手が気にかけるものを気にかけ、相手が重要視し大切にするものを同じように扱う。時にそれは相手が大切にしているから、であるかもしれないが、時にその人がそのことを大切に思う気持ちを自らに取り込むこともある。故人と過ごした時間や、故人との関係のなかで与えられたものは自らの中に取り込まれ、「自分は故人の代理として歩んでいるのだと感じることが出来る」と言う。「 故人が生来ていた時に私たちの生活の網に織り追まれた気づかいの糸を、私たちの生活の新たに統合されたパターンにあらためて織り込む。私たちは、かつて故人と生きた人生を解釈しなおし、現在の生き方を変え、未来に新たな希望と目的を抱きながら、いまでは終わってしまった人生の物語の価値と悪味を自分自身の人生の物語に組み込む」のだという。
適応へのモチベーション
トーマス・アティッグは自身のウェブサイトの中でレジリエンスについて聞かれ、なぜグリーフに退却せず、一歩を踏み出すべきなのか、そのモチベーションについて、このように答えています。人間は前を向いて歩いていくものだ、と言う前提で、ウェブを編み直そうとする原動力は、自ら自身の中に見つけ出すことが出来ると述べています。
私は、誰でも、最悪のグリーフを通り抜けさせる動機や意欲と言うのがあるのではないかと感じています。それを利用する事を簡単に出来る人と、そうでない人がいるようですが。それでも、私たちはそれを私たち自身の中に、時には周りにの人の力を借りて、見つけ出すことが出来ると思います。
それは、私たちの一部(魂、と呼んでおきます)が「人生で最悪の事が起こってしまったが、ここにいる事に意味がある。自分自身の深いところで、自分が世界からもらった、無視するにはあまりにも貴重な恵みや贈り物と繋がろう、深く大切にしていこう、(出来れば)楽しもう、という衝動を感じる。再び人生に自分自身を浸す、自分自身である、ばらばらになってしまったウェブを編み直すというアイディアに魅かれる。今すぐ認めるのは難しいことだが、人生の中で、多くの良い事が私にも起こりえるし、私は周りの残骸をかき分け、継続する意味を取り戻し、抱きしめるのだと信じている」と言うような感じです。
そして、それはまた、私たちの他の一部(霊、と呼んでおきます)が「人生で最悪の事が起こってしまい、私がすごく気に入っていた人生の多くを台無しにしてしまったが、それでも、未知の未来に挑む価値がある。自分自身の深いところで、まだ存在しない物、まだ自分がなっていない者にYESと言いたいと感じる。敗北と見えるようなことを許容することはやめ、その上に立ち上がるのだ。私を押しつぶしてしまいそうな痛みの中で、避けられない物事や、したくもないような変化の中から、それでも一番良い物を拾い上げ、逆境を乗り越え、新しいものに形を合わせ、混沌に意味を与え、その上に勝利を収めるのだ。」と言うような感じです。
私には、こういった気持ちが、喪失の苦しみの中で揺らいでいる、信念、希望、そして愛を最も基本的に肯定するものではないかと思います。これがレジリアンスの核となるもの、勇気の心持なのです。
(トーマス・アティッグのホームページ「Grief's Heart」より)